子どもの歯の生えかわり時期と注意点・よくある疑問を解説
こんにちは。東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院です。

お子さまの歯がグラグラし始めたり、抜けたあとに新しい歯が生えてきたりする様子に、不安や疑問を感じたことはありませんか。歯の生えかわりは成長の大切な節目ですが、時期や流れに個人差があるため「これで大丈夫なのか」と心配になる方も多いでしょう。
適切な知識がないまま放置してしまうと、歯並びや噛み合わせに影響が出ることもあるため、正しい理解がとても重要です。
今回は、歯の生えかわりの時期や、歯の生えかわりの時期に注意することなどについて解説します。
目次
歯の生えかわりとは

歯の生えかわりとは、役目を終えた乳歯が抜け落ち、代わりに一生涯使うことになる丈夫な永久歯へと置き換わる、自然な成長の過程を指します。
乳歯は、お子さんの成長に合わせて生える一時的な歯で全部で20本あり、永久歯は一生使うことを前提にできた強固な歯で親知らずを含めると最大32本あります。
つまり、歯の生えかわりは、お子さんの成長に伴い顎の大きさや噛む力が変化し、小さな乳歯から、より大きく強固な永久歯へと適応していくために起こります。
歯の生えかわりの時期と順序

子どもの歯は、成長に伴って乳歯から永久歯へと順番に生えかわっていきます。その時期には個人差があるものの、一般的には6歳頃から始まり、12〜13歳頃までにほとんどの永久歯が揃います。
最初に生えかわるのは、下の前歯(中切歯)で、6〜7歳頃に抜けて永久歯が生えてきます。次に上の前歯が生えかわり、その後、側切歯・小臼歯・犬歯と順に進んでいきます。
奥歯に関しては、第一大臼歯(いわゆる6歳臼歯)が乳歯の奥に新しく生えてくるため、抜ける乳歯はありません。第二大臼歯は11〜13歳頃に生え、親知らず(第三大臼歯)は17歳以降に生えることが多く、個人差が大きい歯です。
この時期には、歯並びや噛み合わせに影響が出ることもあるため、定期的に歯科検診を受けて経過を確認することが大切です。永久歯が正しく生えるスペースがあるか、乳歯が自然に抜けるかなどをチェックすることで、将来的な歯列不正の予防にもつながります。
歯の生えかわりの時期の注意点

子どもの歯の生えかわりは、成長に伴う自然な変化ですが、正しく進まない場合は将来的な歯並びや噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。以下のポイントに注意して見守ることが大切です。
生えかわりの順序が極端にずれる場合
通常は下の前歯から始まり、奥歯へと順に進みます。順序が大きく乱れている場合は、歯ぐきの中に埋まったままの埋伏歯や、通常より本数の多い過剰歯などの異常が隠れている可能性があるため、歯科医院での確認が必要です。
永久歯がなかなか生えてこない場合
乳歯が抜けたのに、数ヶ月以上永久歯が生えてこない場合は、萌出遅延や位置異常が考えられます。そのため、レントゲン検査で確認することが推奨されます。
乳歯がなかなか抜けない場合
永久歯がすでに見えているのに乳歯が残っている場合、重なり合って生える状態になることがあります。自然に抜けるのを待つか、歯科医院で抜歯を検討することもあります。
歯並びや噛み合わせの乱れが見られる場合
この時期は、歯列が不安定になりやすく、隙間ができる、歯が傾くなどの変化が見られます。これらは一時的なこともありますが、継続する場合は矯正相談も視野に入れましょう。
乳歯が抜けた直後の場合
歯が抜けた部分は傷つきやすく、細菌感染のリスクもあるため、指や舌で触らず、清潔な状態に保つことが大切です。また、抜けた歯を誤って飲み込んでしまった場合でも、通常は心配ありませんが、気になる症状があれば歯科医師に相談しましょう。
歯の生えかわりの時期は通院したほうがよい?

歯の生えかわりが始まってから完了するまでの期間は、先述したように一般的に6歳ごろから12歳ごろまでの約6年間が目安です。
この期間中は、定期的な歯科医院への通院が口腔内の健康維持にとって非常に重要です。理想的な定期検診の頻度は3〜6ヶ月に1回程度で、生えかわりの進行状況や歯列の変化を確認することで、虫歯や歯肉炎の予防にもつながります。
もし乳歯が抜けない、永久歯がなかなか生えてこない、歯並びが乱れているなどの異常が見られる場合は、必要に応じて月1回〜数回の診察が推奨されます。早期に対応することで、将来的な歯列不正や咬合異常を防ぐことができます。
また、歯列不正が疑われる場合には、9〜12歳頃に一度、矯正専門医による診断を受けるのが望ましいとされています。この時期は顎の成長と歯の生えかわりが重なるため、矯正治療のタイミングを見極めるうえでも重要なポイントです。
歯が生えかわることで得られるメリット

ここでは、歯が生え変わることで得られるメリットを解説します。
噛む力の向上
乳歯から永久歯へと移行することで噛む力が大きく向上します。永久歯は乳歯に比べて歯根が長く、歯を構成するエナメル質や象牙質といった組織も厚くなるため、しっかりとした咀嚼が可能です。
一般的に、永久歯が生え揃う12歳前後には噛む力が成人の70~80%程度まで発達するとされており、これにより硬い食べ物も十分に噛み砕くことができるようになります。
ただし、永久歯が生え始めた時期は歯ぐきが敏感になりやすいため、無理に硬いものを食べさせるのは避け、徐々に慣らしていくことが大切です。
発音や顔立ちへの良い影響
歯の生えかわりは、発音や顔立ちに良い影響をもたらします。乳歯から永久歯に移行する過程で、歯並びが整うことで正しい発音がしやすくなり、特にサ行やタ行などの発音が明瞭になります。
また、永久歯が生えそろうことで顎の成長が促され、顔全体のバランスが整いやすくなります。歯並びが良いと笑顔にも自信が持てるようになるでしょう。
虫歯予防への意識づけ
生えかわりの時期は、歯磨き習慣を見直す良いタイミングです。永久歯は一生使う歯なので、子ども自身が歯の大切さを意識するきっかけにもなります。
また、生えかわりをきっかけに定期検診を始めることで、歯科医院への抵抗が減り、将来的な口腔トラブルの予防にもつながるでしょう。
歯の生えかわりに伴うデメリット
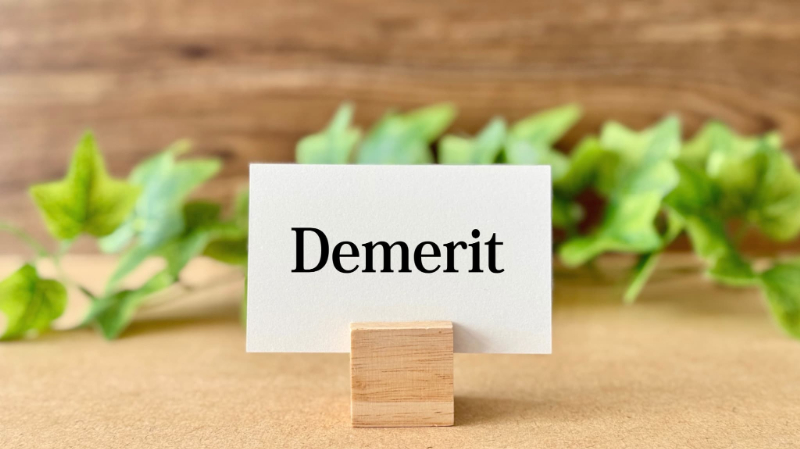
歯の生えかわりは成長に伴う自然な現象ですが、口腔内の環境が大きく変化するため、注意すべき点や一時的な不都合も存在します。
子どもが不安や違和感を覚えやすい
歯が抜けることへの恐怖や、噛みにくさ、違和感などから、食事や会話にストレスを感じる子もいます。保護者の方による声かけや歯科医院での説明が安心につながります。
歯並びの乱れリスク
乳歯が抜けるタイミングや永久歯の生え方によっては、歯並びが一時的に乱れることがあります。特に顎の成長と歯の大きさのバランスが取れない場合、永久歯が正しい位置に生えにくくなることもあるため、定期的な歯科受診が推奨されます。
虫歯や歯肉炎のリスク増加
生えかわりの時期は歯がぐらついたり、歯と歯の間に隙間が生じたりしやすくなります。そのため、食べかすが残りやすく、適切なケアを怠ると虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
一時的な食事のしづらさ
乳歯が抜けて新しい永久歯が生えてくるまでの間は、前歯や奥歯に隙間ができやすく、食べ物をしっかり噛み切ることが難しくなります。特に6歳から12歳頃は生えかわりのピークであり、この期間は硬いものや繊維質の多い食材を避けるなど、食事内容に注意が必要です。
また、歯ぐきが敏感になっているため、熱いものや冷たいものがしみやすくなることもあります。食事の際は無理に噛まず、小さく切るなど工夫をすると良いでしょう。
歯の生えかわりに関するよくある質問

歯の生えかわり時期によくある質問と回答をご紹介します。
生えかわりが遅い
生えかわりの時期には個人差があり、周囲と比べて遅い場合でも多くは心配ありません。
ただし、明らかに遅れている、左右で差が大きい、痛みや腫れがある場合は、歯科医院で相談することが推奨されます。
乳歯が抜けない
乳歯が抜けない場合、無理に引き抜かず、自然に抜けるのを待つことが基本です。
ただし、7歳を過ぎても前歯が抜けない場合や、永久歯が重なって生えてきた場合は、噛み合わせや歯並びに影響することがあるため、早めの相談が大切です。
乳歯が抜けていないのに永久歯が生えてきた
永久歯が乳歯のうしろや内側から二重に生えてきた場合、まずは乳歯が自然に抜けるか1〜2週間程度様子を見ます。それでも抜けない場合や永久歯が大きくずれている場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。
乳歯が残ったままだと歯並びが悪くなるリスクが高まるため、抜歯をすることもあります。特に6〜8歳ごろの前歯や、10〜12歳ごろの奥歯の生えかわり時期に多く見られるため、この時期は注意深く観察することが大切です。
まとめ

子どもの歯の生えかわりは、成長の大切な過程のひとつです。一般的に6歳頃から始まり、12歳頃までに永久歯へと順番に生えかわっていきます。
この時期は乳歯と永久歯が混在することで、歯磨きが難しくなり虫歯のリスクが高まるため、丁寧なケアが求められます。
また、歯並びや噛み合わせの変化にも注意が必要です。生えかわりの期間中は、歯科医院で定期的にチェックを受けることで、トラブルの早期発見や適切なアドバイスが得られます。
生えかわりには、健康な永久歯が生えてくるというメリットがある一方で、違和感や痛み、歯並びの不安などデメリットも考えられます。疑問や不安がある場合は、早めに歯科医師へ相談すると安心です。
お子さんのお口の健康を守りたいとお考えの保護者の方は、東京都文京区「江戸川橋駅」より徒歩1分にある江戸川橋菊地歯科医院にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・歯周病治療をはじめ、根管治療や小児歯科、矯正治療にも力を入れています。診療案内ページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。


